研究活動 活動報告
2018年度第4回公開シンポジウム「遺跡に見る在来知-モニュメント、自然環境、インターアクション」実施
2018年12月26日
2018年度公募シンポジウム「"在来知"のゆくえ」
 ポスターをダウンロード ポスターをダウンロード |
[日時]2018年12月26日(水)、13:00~17:30(開場12:30)
[会場]南山大学S棟・S46教室
[主催]南山大学人類学研究所
[プログラム]
・発表1:「なぜ古代人はピラミッドを造ったのか:メキシコ中央高原における都市の盛衰」
嘉幡茂(ラス・アメリカス・プエブラ大学・准教授/京都外国語大学・客員研究員)
フリエタ・M.=ロペス・J.(京都外国語大学・客員研究員/メキシコ国立自治大学・博士後期課程在籍)
・発表2:「神殿間のネットワークと在地性:アンデス形成期の事例」
松本雄一(山形大学・准教授)
・発表3:「噴火災害をどう乗り越えたか:古代マヤ人の火山とともに生きる知恵・記憶」
市川彰(名古屋大学高等研究院/人文学研究科・特任助教)
・発表4:「中央と在地社会:古代アンデス諸国家の事例」
渡部森哉(南山大学人類学研究所/人文学部・教授)
・コメント1:後藤明(南山大学人類学研究所/人文学部・教授)
・コメント2:中尾央(南山大学人類学研究所/人文学部・准教授)
[開催趣旨]
遺跡の発掘調査をしていると、しばしばその土地の「在地の」「土着の」モノと外来のモノを識別して考える。外来のモノは他に起源がある場合に、つまりより古い時代に認められる場合に、そこからもたらされたと考えられる。
しかし翻って、「在地の」とは何を示しているのであろうか? 英語でローカルという場合、その土地に認められるということと同時に、他の地域では認められないということも想定している。本シンポジウムでは、ローカルに認められる経験、知識がどのように物質文化に認められるのかを、考古学データから分析することを目的とする。過去の事例を扱うことによって数世代にわたり知識がどのように維持、変化していくかを考察する。それは一人の人間が観察できる時間幅を超えた現象であり、しばしば当初は意図していなかった結果がもたらされることもある。
本シンポジウムで扱うのは中南米の事例である。特に複雑社会が現れた後の時代を取り上げる。旧世界では複雑社会は文字を伴う場合が多く、考古学データの解釈は常に文字資料の内容と突き合わせることによって解釈される。一方、文字資料が見つかっていない場合、遺跡の発掘データを純粋に物質文化の視点のみから解釈することができる。物質文化の研究から、それに関わる人々の知識にどれだけ迫れるかを試みる。
分析の視点として、モニュメント、自然環境、インタラクション、という3つのキーワードを挙げる。
考古学では一般に大規模な建築物などをモニュメントと呼ぶ。モニュメント建設には多くの時間と労働力が費やされるため、その社会の特徴が凝縮していると見ることができる。モニュメントにどれだけ在地性が認められるか、それが何に起因するのかに着目する。
自然環境は所与の条件であるが、人類はある程度それを改変する力を持っている。また、自然災害などにどのように対応したのかなどに着目することで、当時の人々が自然環境をどのように理解していたかを分析する。
インターアクションは、しばしば複数の社会単位間での動きを説明するために用いられる概念である。他地域、他の社会集団との相互交流を通じて、共通性も生まれるが、同時に差異化のメカニズムも働き、他地域とは異なる点に在地、土着の特徴を認めることができる。インターアクションから在地性が顕在化する仕組みを分析する。
[発表要旨]
◆発表1:「なぜ古代人はピラミッドを造ったか:メキシコ中央高原における都市の盛衰」
嘉幡茂、フリエタ・M.=ロペス・J.
要旨:
古代メソアメリカ文明でも数多くのピラミッドが建造された。ピラミッドには、王のお墓というイメージが付きまとう。しかしそれは、ピラミッドの用途の一側面を表しているに過ぎない。ピラミッドの本来の存在理由は別の所にある。ピラミッドには、建造を指揮した為政者らの異なる思想が反映されている。どのように社会を導き、どのように自身の社会的役割を人々に見せ、そして、どのように彼らの要望に応えようとしたのかである。この相違が、数多く存在するピラミッドの大きさや形状そして壁面への装飾に多様性をもたらした。同時に、いくつかの古代都市を発展させる原動力にもなり、他方、衰退を引き起こす要因にもなった。本発表では、ピラミッドの存在理由と世界観をキーワードとして、古代メソアメリカ文明のメキシコ中央高原における都市の盛衰について議論する。事例として、トラランカレカ(前800~後300年)、テオティワカン(前150~後550/600年)、そして、チョルーラ(前200~後600年)の三都市を取り上げる。
◆発表2:「神殿間のネットワークと在地性 --アンデス形成期の事例」
松本雄一
要旨:
古代アンデス文明の初期にあたる形成期(紀元前3000-50年)という時代は、神殿を中心として社会が統合されていた時代であると定義される。この時期には、神殿をつくるという行為自体が社会の統合を促し、遠隔地間の交流を活性化させることとなり、その結果として、各地の社会は神殿そのものの建築様式、物質文化、宗教的信仰など様々な点で地域を超えた共通性と在地的な独自性の双方を保持することとなった。本発表では、アンデス文明の初期形成において長く「周縁」とみなされてきたアンデス南高地の神殿を取り上げ、形成期後期(紀元前800-500年)に中央アンデスの広い地理的範囲に宗教的影響を及ぼしたとされるチャビン・デ・ワンタル神殿と同地域との交流に焦点を当てる。双方の神殿建築と物質文化の変遷を通時的に比較することを通じて、外来と在地の異なる宗教的信仰がどのように接触し変化したか、またそのプロセスがどのように社会変化と関わっていたかを考察する。
◆発表3:「噴火災害をどう乗り越えたか:古代マヤ人の火山とともに生きる知恵・記憶」
市川彰
要旨:
人類はいかに急激な環境変化に対応してきたのか。寒冷化や温暖化のように長期的周期で生じる環境変化に加え、世界規模での災害被害もあり、突発的・短期的周期で急激な環境変化を促す「災害」への社会的・学術的関心は高い。突発的な危機への対応は人間社会の本質が見え、それは往時の技術、価値観、社会のあり様などによっても異なる。本発表で取り上げるのは「噴火災害」である。テオティワカンやマヤ文明が栄えたメソアメリカには数々の火山があり今なお活発な火山活動が見られるが、火山を中心とする自然景観は集落や都市の選地や信仰とも深く関連している。本発表では、マヤ南東地域における4度の火山噴火(紀元後450年頃650年頃、1000年頃、1658年)の事例を中心に取り上げながら、古代の人々がどのように噴火災害に対応したのか、考察する。同時に、噴火の前後の物質文化の変化の有無に着目しながら、火山とともに生きる知恵や記憶への接近を試みる。
◆発表4:「中央と在地社会:古代アンデス諸国家の事例」
渡部森哉
要旨:
中央アンデス地帯には、前3000年頃から神殿建設が始まり、約3000年間続いた。その後、後1世紀頃にアンデスの初期国家が成立した。アンデスの国家の特徴の1つは、首都とされる遺跡が肥大しているという点にある。先スペイン期最終期に台頭したインカ帝国では、首都クスコの荘厳さ、規模は飛び抜けている。先インカ期の国家社会でも、チムー、シカン、ワリ、ティワナクなど、いずれも首都の存在は際立っている。また、首都を中心とした地方統治のために、各地に地方行政センターが設置されたが、首都のコピーという特徴もあるが、多くの場合は各遺跡の独自性が目立つ。そして中央からの一方向的な支配ではなく、在地社会の主体性を認める研究者は、地方独自の特徴に目が向きがちである。本発表では、中央が巨大な一方で、各地方にローカル性が現れるというアンデスの国家社会の特徴を考察する。インカ帝国とワリ帝国に焦点を当て、統治システムと物質文化の関係性に着目する。
[報告]
2018年度に人類学研究所では「"在来知"のゆくえ」をテーマにシンポジウムを公募した。審査の結果、メキシコの大学で教員をしている嘉幡茂氏を代表とする「遺跡に見る在来知」が採択された。嘉幡氏が日本に一時帰国する日程に合わせて、12月26日に開催された。
「在来知の生成・継承・革新・消滅・再起・利用」などを遺跡のデータからどのように再構成できるかが公募シンポジウムの要項に記載されているが、今回のシンポジウムでは考古学的に長期的視点から、ローカルな特徴がどのように認められるかを4名の発表者が考察した。
嘉幡・ロペス報告は、メキシコ高原地帯の3つのモニュメントを事例として、それらの建設、衰退の要因を考察した。松本報告はアンデス形成期の代表的遺跡であるチャビン・デ・ワンタルとの関係で周辺とされる地域の神殿の関係について分析し、ローカルな現象の重層的な特徴を論じた。市川報告はエルサルバドルを事例として、火山噴火という出来事を契機とした在地社会の変容、あるいは継続性について論じた。最後に渡部報告は、古代アンデスの国家社会であるインカとワリを事例として、ローカルとされる現象がいくつかに類型化できることを論じた。
コメンテーターである後藤明氏は文化人類学・オセアニア研究の視点から、中尾央氏は科学哲学・科学論の立場から、各報告についてコメントした。
 |
 |
 |
| 嘉幡茂氏 | 松本雄一氏 | 市川彰氏 |
|
|
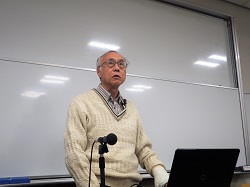 |
 |
| 渡部森哉氏 | 後藤明氏 | 中尾央氏 |
 |
||
| 多くの人にお集まりいただきました |
