スタッフ紹介
所長

渡部 森哉(WATANABE, Shinya)
人文学部人類文化学科・教授
アンデス考古学・文化人類学。古代アンデスの複雑社会を主な研究テーマとしている。インカ帝国(後15-16世紀)と、その祖型とされるワリ帝国(後8-10世紀)の研究を、ペルー北部高地カハマルカ地方を事例としながら進めている。遺跡の発掘調査と、植民地時代の記録文書の分析を行っている。第一種研究所員

ドーマン ベンジャミン(DORMAN, Benjamin)
ノミナル所属:外国語学部英米学科・教授
Most of my publications have focused on media representation and spirituality in Japan. I looked in particular at new religious movements in Japan during the period of Allied Occupation (1945-1952). While I am still interested in media representation and spirituality, I am now working on views of disability in society, particularly Japan and the United States, with a focus on autism spectrum disorder. Apart from my research, I am the co-editor of Asian Ethnology, which is published at this Institute.
宮脇 千絵(MIYAWAKI, Chie)
ノミナル所属:人文学部人類文化学科・准教授
文化人類学。人が装うことの意味をフィールドワークに基づき研究しています。これまで中国西南地域に居住するモン(ミャオ族)の「民族衣装」の変化に着目してきました。最近は、その国境を越えた流通と消費を追いながら、人が装うものを生み出し、求める行為を多角的にとらえる試みをしています。高柳 ふみ(TAKAYANAGI, Fumi)
人類学博物館担当学芸員・講師
文化人類学・博物館学。これまでオーストリアのチロル州でフィールドワークを行い、放牧に関する映像民族学的研究をしてきました。近年は、ドイツ語圏の民族学博物館が所蔵するサーミ・コレクションを事例に、その来歴を20世紀初頭の社会的・政治的背景をふまえて考察し、ソースコミュニティとの協働や新しい資料活用の可能性などについて研究をしています。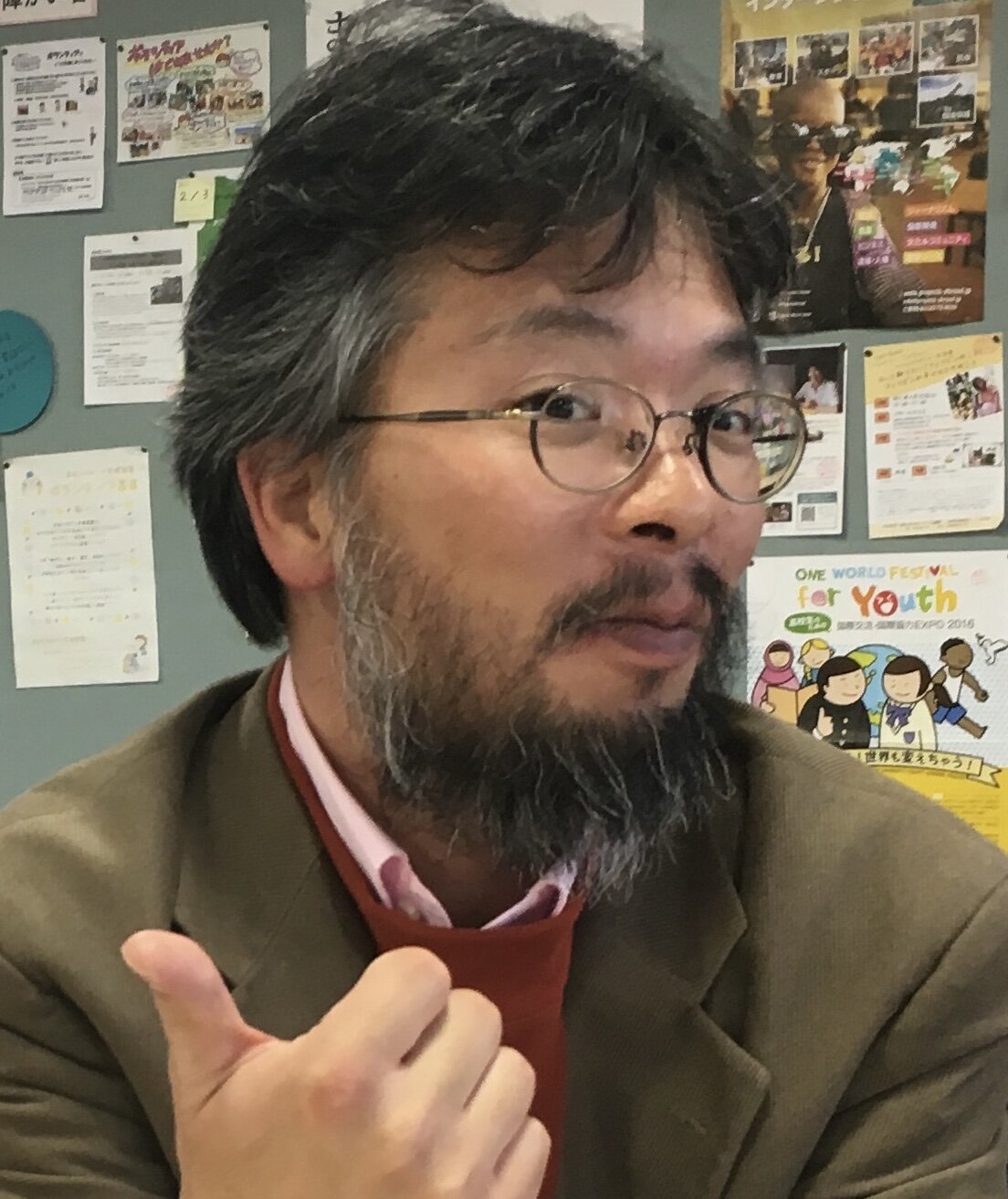
鈴木 康二(SUZUKI, Koji)
人類学博物館担当学芸員・准教授
先史学(考古学)/博物館教育/保育(幼児教育・療育)。先史時代の生業や文化について、当時の人々の価値観や意識を知るべく、主に考古学的手法に拠りながら研究をしています。特に当時の社会における「こども」像の具体化・具現化が現在のテーマです。また博物館活動を通じて、現在の「こども」を取り巻く状況が、少しでも「こどもの思い」に寄り添ったものになるように考えていきたいと思っています。第二種研究所員

石原 美奈子(ISHIHARA, Minako)
人文学部人類文化学科・教授
文化人類学。北東アフリカのエチオピアの南西部に住んでいるムスリム・オロモの人々の宗教の営みや地域の歴史について調査研究しています。イスラームというと昨今の報道では暴力的で「危険」というイメージが強いですが、エチオピアの場合は急進的な復興主義の立場をとる人は少数派です。なぜエチオピアのイスラームが総体的に穏健なのか、私は主としてムスリム宗教指導者の個人史を集めるという手法をとりながら、考えてきました。最近は、ムスリム宗教指導者の知の営みに着目して、教育のあり方や彼らが書き残したものを対象に研究を進めています。
川浦 佐知子(KAWAURA, Sachiko)
人文学部心理人間学科・教授
アメリカ合衆国モンタナ州に保留地をもつノーザン・シャイアンの人々の語りを通して、主流社会と相容れない世界観をもつ先住民の人々の記憶継承の在り様について検討しています。近年はミュージアム展示の在り様について目を向け、先住民の側から発信される共同体の歴史についても検討しています。
クロッカー ロバート(CROKER, Robert)
総合政策学部総合政策学科・教授
質的研究、フィールドワークの方法論について研究しています。最近は、日本人学生とタイ人、マレーシア人、アメリカ人などの学生とフィールドワークの手法について、共に考え実践しています。また日本における人類学的調査の教育方法にも関心を持ち、研究をすすめています。
張 玉玲(ZHANG, YuLing)
外国語学部アジア学科・教授
華僑華人研究、文化人類学。主に日本におけるチャイナタウンの観光化に伴う伝統文化の資源化と華人アイデンティティとの関連について研究してきました。最近は、中国の改革開放政策実施後に増加したいわゆる「新華人」の定住によって、大きく変化しようとする華人コミュニティの構造について調査研究を進めています。
藤川 美代子(FUJIKAWA, Miyoko)
人文学部人類文化学科・准教授
社会人類学・文化人類学。東南中国の船上生活者のもとでフィールドワークをしながら、「水上に住まう」とは、定住/遊動とはいかなる営みなのかを考えてきました。最近は、近現代の日本にも調査範囲を広げ、船上生活者の「陸上がり」プロセスにつきまとう国家の管理/救済の形を明らかにする取り組みを始めています。
ムンシ ロジェ ヴァンジラ(MUNSI, Roger Vanzila)
国際教養学部国際教養学科・教授
社会文化人類学・歴史民俗資料学・宗教学。コンゴ民主共和国(旧ザイール)出身。コンゴ・サカタ族を中心にアフリカの伝統的精神文化や、キリスト教の影響を研究。日本ではかくれキリシタンとキリシタン神社の調査研究に従事しており、目下、キリシタン神社の歴史と現状に関して研究をすすめている。
吉田 竹也(YOSHIDA, Takeya)
人文学部人類文化学科・教授
文化人類学。インドネシアのバリの宗教の研究から出発し、バリおよび沖縄の「楽園観光」研究へと主題を展開しています。文化人類学に社会学や島嶼学などの研究を織り込み、管理化・個人化の進む現代社会で「楽園」での癒しを求める観光者とそれを受け入れる観光地社会の人々について考察しています。
リースラント アンドレアス(RIESSLAND, Andreas)
外国語学部ドイツ学科・准教授
Presently, my research is focused on aesthetics and of images of nature as a criteria in the Japanese national discourse, and of their manifestation in Japanese advertising in the secon half of the Showa era. Another field of interest is the self-enactment of fringe groups in Japan's late modern society, as well as their perception in mainstream society and the media.プロジェクト研究員

髙村 美也子(TAKAMURA, Miyako)
プロジェクト研究員(受入所員・石原美奈子)2020/4/1任用
文化人類学。スワヒリ文化圏であるタンザニアの農村ボンデイ社会にてフィールドワークを行い、ココヤシの利用に焦点にあて、スワヒリ農村の暮らしについて研究してきました。最近は、農村に根付いている「相互協力」のあり方を、伝承文化と社会環境の関係から明らかにする取り組みをしています。
竹内 愛(TAKEUCHI, Ai)
プロジェクト研究員(受入所員・宮脇千絵)2020/4/1任用
文化人類学。ネパールのカトマンズ盆地に居住するネワール民族の女性自助組織の多様な活動とそれによる女性たち自身への影響や社会変容について調査研究をしてきました。2015年ネパール大地震が発生してからは、震災復興過程に女性自助組織がどのような役割を果たしているのかに関心を持って研究を進めています。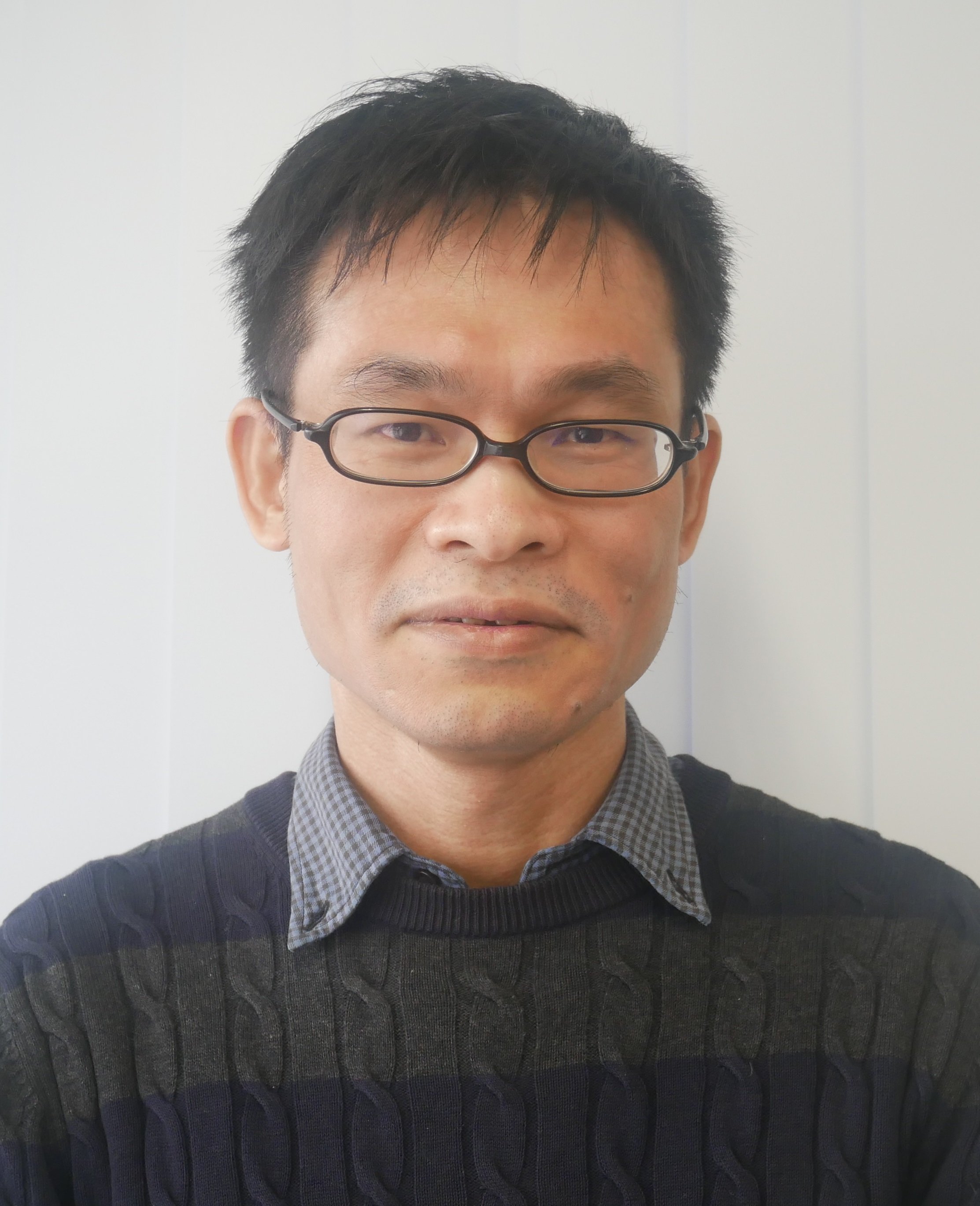
加藤 英明(KATO, Hideaki)
プロジェクト研究員(受入所員・石原美奈子)2022/4/1任用
文化人類学。現代の工業社会のモノづくりを研究しています。とくに自動車産業に関わる町工場の人びとを対象に、機械化により生み出される技や知のあり方を民族誌的手法に基づき研究しています。最近では3Dプリンターに着目し、技術がもたらす創造性がどのように技術革新に結びつくのかに関心をもっています。
カポビアンコ ポール ジョセフ(CAPOBIANCO, Paul Joseph)
プロジェクト研究員(受入所員・DORMAN, Benjamin)2023/11/1任用
My project focuses on how Japanese language and culture have intersected in the formation of Japanese identity in the past and in the present. I am especially interested in understanding the ways that cultural practices, nonverbal communication, and other cultural forms intersected with language to inform notions of Japanese identity historically.This research aims to explore the role of culture and language specifically to understand the root mechanisms behind this reification of non-Japanese actors into the Japanese majority.
デンロンデン ハーモニー(DENRONDEN,Harmony)
プロジェクト研究員(受入所員・DORMAN, Benjamin)2023/12/1任用
At the beginning of the 21st century, English remains the dominant language of international academic publishing. This places scholars raised outside of English-speaking countries at an immediate disadvantage. One goal of Asian Ethnology, published by the Nanzan University, Anthropological Institute. is to introduce important anthropological research by Asian scholars to an international English-language audience. This research aims to examine the impact of publication in Asian Ethnology on early career researchers' academic career trajectory, especially those of non-native-English background.非常勤研究員
| 氏名 | 研究課題 | 受入期間 | 受入所員 |
|---|---|---|---|
| 小坂 恵敬 | パプアニューギニアを対象とした第二次世界大戦の現在への影響に関する人類学的検討 | 2025年4月~2026年3月 | 渡部森哉 |
| 野澤 暁子 (名古屋大学・共同研究員) |
中世ヒンドゥー・ジャワ文化遺産の芸術人類学的研究 | 2025年4月~2026年3月 | 吉田竹也 |
| 梅津 綾子 (名古屋大学大学院(JSPS-RPD)) |
多様な家族、子育て、性、信仰のあり方―アフリカ、ムスリム・ハウサ社会の「里親養 育」慣行、および日本のLGBT ムスリムを事例に | 2025年4月~2026年3月 | 渡部森哉 |
| 辻 輝之 (広島大学・准教授) |
1. 異なるアジアの邂逅:移民の宗教・エスニシティ共生・社会関係資本 2. 紛争論再考:多宗教共存・エスニシティ共生 | 2025年4月~2026年3月 | 渡部森哉 |
| 岡本 圭史 (九州大学大学院人間環境学研究院・学術協力研究院) |
アフリカ都市の神学的思索に関する宗教人類学的研究 | 2025年4月~2026年3月 | 宮脇千絵 |
| 廣田 緑 (国際ファッション専門職大学・准教授) |
木版画を媒体とした現代美術の実践と社会的役割 インドネシアとマレーシアを事例に | 2025年4月~2026年3月 | 吉田竹也 |
| PETERSEN, Esben (Assistant Professor, Kwansei Gakuin University) |
The Ambivalence of Utopian Ideals in Modern Japan: Christianity's Role in Disseminating the Colonial Fairy Tale of Denmark as a Happy and Self-Sustaining Agricultural Society | 2025年4月~2026年3月 | DORMAN, Benjamin |
| 菅沼 文乃 (三重大学・准教授) |
沖縄における老いの様相に関する人類学的研究 | 2025年4月~2026年3月(新規) | 石原美奈子 |